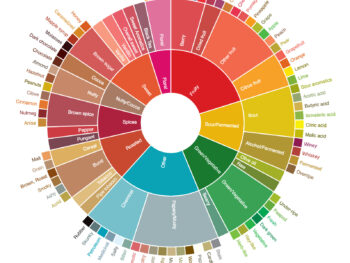「早くも黄昏(たそがれ)てんじゃねぇよ!」
昔の仕事仲間が、現在の筆者の様子を知って放った一言である。
実に辛辣だが、悪意は感じられない。
どうやら、コーヒーとサーフィンに没入する筆者が、
彼の眼には、奇異に映ったらしい。
そこで今回は、人生の黄昏時を感じつつも、
情熱を傾ける事柄がまだまだ残っていることに幸せを感じずにはいられない
珈琲人の心模様を綴ってみたい。

「たそがれ」とは?
もちろん、「たそがれ」とは、
日が暮れる様子を表す言葉であり、日本語らしい美しい言葉でもある。
街灯などが無かった江戸時代以前は、
夕暮れになると通りを歩く相手の顔の判別が難しかった。
そのような場面で、
「誰そ彼(たそかれ)?」
と問いかけていたそうだ。
つまり、「どなたですか?」と尋ねていたのである。
その問いかけの言葉が、
日暮れ時を表す言葉に転じたのが「たそがれ」の語源である。
実に優美な言葉ではないか。
また、夕暮れ時の比喩として、
「人として衰え始める」という意味でも「たそがれ」が用いられるようになった。
すなわち、先の旧友に投げかけられた「黄昏てんじゃねぇよ!」は、
「早くも衰えて、どうしちゃったの?」
という意味で発せられたものなのだ。
今もビジネスの最前線をひた走る彼の価値観では、
現在の筆者の生き方は、どうにも測りかねるらしい。
ちなみに、「たそがれる」には、
「物思いに耽る」という意味は無いことを言い添えておきたい。
時折、この「物思いに耽る」趣旨として「たそがれる」を用いる場面に遭遇する。
むろん、言葉は時代と共に変化するものではあるが、
今のところ、「物思いに耽る」というニュアンスでの「たそがれる」には、
どうしても違和感を感じずにはいられない。

たそがれて候(そうろう)
衰えを初めて自覚したのは、確か40代に入った頃だったように記憶している。
読書好きの筆者は、常に10冊程度の本を枕元に置く習慣があった。
傍らに本があると安心して熟睡できるからだ。
そんなある夜、就寝前の読書をしていると、どうにも文字が読みづらいことに気付いた。
驚いたのはそこからで、焦点を合わせようと頭を後ろへのけぞらせていたのである。
老眼を初めて自覚した瞬間だ。
その衝撃は、思いのほか大きなものであった。
他にも、髪の毛は薄くなり、その上で白髪が目立っている。
しわとは無縁と思っていたことがまるで幻のように、
鏡の中に映し出された顔には、しっかり年相応のしわが刻まれてもいる。
他にも色々とあるのだが、挙げればきりが無いのでこの辺りにしておきたい。
男としての盛りを過ぎて衰えを自覚する日々。
そう、人生のたそがれ時を迎えた筆者は、正に
「たそがれて候」
なのである。

真剣勝負のコーヒー
しかし、コーヒーに関しては、たそがれている訳にはいかない。
自分で評するのも滑稽だが、
コーヒーに向き合う姿勢は、さながら10代の青年が恋人と接する様である。
好奇心が尽きず、相手のことを深く知りたい欲求に駆られてしまう。
「もっと、もっと」
となるのである。
いわゆる、「情熱の塊」とでも云うべきか。
相手の表情に、一喜一憂することになる。
また、知れば知るほど興味が掻き立てられるのであるから、
コーヒーとは、実に奥が深く、魅惑的な飲み物なのだ。
特に、焙煎における「化学反応(=ケミカルリアクション)にはゴールが無い。
変数が多すぎて、絶対的な答えが見出せないのが魅力だ。
故に、コーヒーと向き合う際は、
仕入れにおいても、焙煎や抽出においても、常に真剣勝負で挑むことになる。
そして、10代の頃のように、目はキラキラといつまでも輝き続けるのだ。

たそがれつつも…
波があれば海に入り、
またある時は、至福の一杯を求めて豆を焼き、そして抽出してわずかながらの贅沢を愉しむ。
たそがれつつも、情熱を傾ける事柄がある幸せを日々噛み締めている。
そう、これも毎日
「自分らしくスウィング」
することが出来ているからだろう。
「好きこそ物の上手なれ」
とはよく云ったものである。
筆者にとっては、コーヒーとサーフィンがこれに当てはまる。
身体的な衰えは、遅かれ早かれ誰にも平等に訪れるが、
精神的な面は、「好奇心」さえ見失わなければ、
いつまでも黄昏ずにいることができるだろう。
若い方にはピンと来ない話かもしれないが、
筆者と年代が近い方々の中には、共感していただける方もいるのではなかろうか?
今回は、人生の黄昏時を迎えた珈琲人の心の声を切り取り綴ってみた。
どのような心持の珈琲人が焼く豆なのか、参考になれば幸いである。