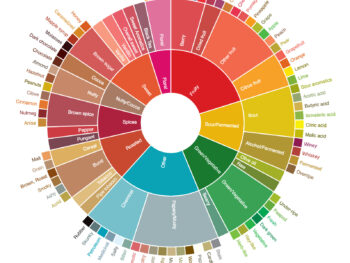死生観とは、生と死に対する自己の考え方のことである。
筆者は、働き盛りの壮年期より折に触れ死生観について自問自答を繰り返していた。
しかし、日本では、宗教色のない平場の環境において、自身の死生観を語る機会は
ほとんど無いに等しい。
いや、むしろ素知らぬ顔で避けているようにも伺えるのだが、そのように感じるのは
果たして筆者だけであろうか?
ゆえに、今回は、
老年期を迎えた筆者の死生観なるものを自身の手控え(=覚書き)として呟いてみることにした。
不思議なことに、若い頃と違って
実にシンプルであることを再認識するとともに、改めてその意を強くしたところである。
死生観について考え始める時期は?
死生観について考え始める適切な時期は、いつ頃が妥当なのであろうか?
筆者の場合、青年期の後半から漠然と考え始めた記憶があるが、
真正面から向き合い始めたのは壮年期に入ってからのことである。
とある苦難に直面したことがきっかけで真剣に思考するようになった。
その時期が早いか遅いかで言えば、遅きに失した感は否めない。
これはあくまでも私見であるが、理想を言えば、子どもの時分より
「人は何のために生きているのか?」
については、その子の年齢に応じて、
家庭の中で、また、学校のクラスメイトと語り合うべきテーマだと考える。
なぜなら、人として向き合うべき最も基本的な観念だからだ。
ところが、残念なことに、
筆者を含め多くの人は、幼少期から「何のために生きているのか?」
を親から知らされず、教師からも教えられず、
また自らも真剣に考えずに毎日をただ漠然と過ごしている。
したがって、筆者のように困難や苦難に直面してから初めて自問自答を始めるか、
あるいは自ら答えを導き出せずに何某かの宗教に助けを求めるか、
はたまた挫折を繰り返しつつ、人生に疲れ果てながらも出口の見えない迷路を
闇雲に歩き続けることになるのだ。
話は逸れるが、日本人の道徳観や倫理観の水準は、世界の中でも高いと言われている。
それは、今に始まったことではない。
古来より続く日本特有の国柄である。
今日の外国人旅行者が、総じて日本人に好印象を抱くのも頷けるというものだ。
しかし、その道徳観や倫理観と同様に、
「死生観も最初に身に付けておくべき大切な素養の一つでは?」
というのが筆者の考えである。
三つ子の魂百までではないが、
幼少期からの精神は、年老いても色あせることなく自らを助けてくれると筆者は確信している。
人生は死ぬこと
「人生と云うは死ぬことと見極めたり」
これは、筆者の座右の銘である。
武士道の処世訓を綴った「葉隠」に登場する有名な一句
「武士道と云うは死ぬことと見付けたり」
を現代風にアレンジしたものだ。
しかし、それは後付けである。
そのように説明した方が伝えやすいため、かの一句を流用しているに過ぎない。
元々はもっとシンプルに、
「生きるとは死ぬことだ」
というのが、深く長い思考の末に帰着した筆者の死生観であった。
生きることは死ぬこと?
正直に告白すれば、最初からこのようにシンプルな死生観を持っていたわけではない。
若い頃は、あれやこれやと考え過ぎ、わざわざ複雑に捉えて悩むこともあった。
「人は何のために生きているのか?」
ただひたすら、この単純な問いかけを続けたのだ。
もちろん、真剣にである。
この問いを突き詰めていくと、
あれこれと考える必要がないこと、
また、わざわざ複雑に捉える必要がないことに思いが至った。
その思いを言葉で表現するのは難しいが、
「知識といった類の頭の中の理解ではなく、身体全体を通じた実感としての理解」
とでも言うべき心境に至ったのである。
つまり、余分な考えや思いをそぎ落としていくと、
「人はただただ死ぬために生きている」
という、至極単純な理が「ドォーン」と強烈な印象とともに、身体全体に降りて来たのだ。
この理が一旦腑に落ちると、
「あとは死を迎えるその日まで、ただひたすらに行動あるのみ」
の思考回路が形成された。
そして、
「死に切るために今を生き切ろう」
という意識が顕在化し、自然と自分を導き始めたのだ。
これが第一段階であった。
続く第二段階は、
「人は何のために死ぬのか?」
或いは、
「人は何のためなら死ねるのか?」
と自問自答を繰り返してみた。
この問いを掘り下げることで、
他人事ではなく、自らの死をリアルに真正面から受け入れられると同時に、
不思議と生のエネルギーが沸き立つ感覚が味わえた。
この感覚も言葉で表現するのは難しいが、
いわゆる、自分の進むべき「道」がおぼろげながらにも見えた精神的高揚とでも言うべきものである。
なお、上記の「人」という不定称を
「私」という一人称に置き換えてみるとより身近に感じられるだろう。
「私は何のために死ぬのか?」
或いは、
「私は何のためなら死ねるのか?」
いかがだろう?
「自分はどのように死ぬのか?」
を突き詰めていくと、
「自分はどのように生きるのか?」
が自ずと自覚できるようになってくるのだから不思議である。
生と死は、対峙する関係ではなく常に表裏の関係、
いついかなる時も背中合わせであるというのが筆者の死生観の根本なのだ。
すなわち、
「生きることは死ぬこと」
というとてもシンプルな理にたどり着くのである。
武士の死生観
かつて、日本に存在した武士階級の人々は、
大義のための死や忠義のための死、或いは名誉のための死を自ら選択することができた。
戦が頻発していた時代においては、
「合戦に赴き死ぬるは武士の本望なり」とばかりに戦場において華々しく斬り死にし、
また、太平の世になってからも、
「主君に忠義を尽くすための死は武士の鏡なり」であったのだ。
さらに、名誉を傷つけられたならば果し合い、
「斬り死にしてもやむなし」が武士の一分でもあった。
言い換えるなら、武士たちは、
「自分は何のために死ぬのか?」
或いは、
「自分は何のためなら死ねるのか?」
の意識が現代人よりも明確であったろうと推察できる。
もちろん、死を選択するしないは本人次第なのだが、
武士階級の死生観は、清々しいほどにハッキリしていたのだ。
とは言え、「葉隠」なる武士道の処世訓が記されたところをみると、
江戸時代中期以降の武士の死生観も、実は案外グダグダだったのかもしれない。
葉隠的な死を選択できない現代人
現代の日本人は、古の武士のように大義のため、忠義のため、名誉のために腹を切ることはない。
いや、出来なくなっているというのが本当だろう。
むしろ、いかなる理由の自死も殺人と同等か或いは同類として禁忌の行為とされている。
三島由紀夫の自刃は、稀代の文学者がその禁忌を破った例外中の例外の一大事件だったのだ。
おそらく三島の自決は、葉隠的な死の最後になるのかもしれない。
一方で、人生に疲れ、挫折を乗り越えられずに将来を悲観して自ら死を選ぶ人は、
武士の時代もいたであろうし、現代では深刻な社会問題にすらなっている。
しかし、現代人の自らの命を絶つ選択は、
武士のような明瞭な死生観に基づく積極的な死の選択とはまったく別物なのだ。
むしろ、死生観を見失った挙句の果ての消去法的選択と言われても仕方がない所業と言える。
このように考えると、現代の日本人は、
葉隠的な死生観に基づく積極的な死を自らは選択できなくなったと言ってもよいだろう。
行動に反映される死生観
繰り返しになるが、「自分はどのように死ぬのか?」を突き詰めていくと、
「自分はどのように生きるのか?」が自覚できるようになる。
つまり、死生観が自らの行動規範となるのだ。
事故死を望まなければ、事故に遭遇する可能性を排除しようと行動する。
もちろん、不慮の死に遭うことも可能性としてはあるのだが、
そうしたことも想定した準備の行動を怠らない。
また、脳疾患や心疾患による突然死を望まなければ、日頃から健康に留意した生活を心掛け行動する。
他の成人病も同様である。
しかしながら、いかに健康に気を配っていたとしても、いずれは病に罹ることもあるだろう。
癌を患うことなどがよい例である。
発見した年齢やステージにより、手術や放射線治療、薬物療法を受けるか放置するのかの決断を下す。
あくまでも決断を下すのは自分自身であり医師ではない。
その決断の拠り所も自らの死生観次第である。
年齢やステージによっては、何の治療も受けずに放置するという選択もあり得るのだ。
最も最悪なのは、死生観を持たないがために、
ただただ生きながらえたい一心で手術を受け、その後も痛みに耐えながら闘病を続けた挙句に、
病院のベッドの上で迎える死ではないだろうか?
死生観を持つとは、死に直面しても不動心を保つことである。
多少の心の揺れは、仏ではなく人なのだから仕方のないことと割切ってしまえばよい。
ジタバタせずに、潔く死を受け入れられればよいのだ。
ちなみに、筆者は既に老齢期に入っている。
人生50年時代を生きた武士の時代からすれば、十分過ぎるほど長生きをしてきた。
加えて、筆者の家系はいわゆる癌家系なのだ。
健康に気を配っていたとは言え、これまで一度も大病を患っていないのが不思議なくらいである。
ゆえに、今後癌であると診断された際の身の処し方は決めている。
一切の治療を受けず、放置して自然死を迎えたい。
本当の最期には、モルヒネの力を借りなければならないであろうから、
そのまま放置して自然死を受け入れることについて医師を説得する手間がかかるのは覚悟の上だ。
もちろん、この方針は、自身の死生観から生まれている。
「生きることは死ぬこと」
「生と死はコインの裏表」
その日がくれば、その方針に従って粛々と行動するのみである。