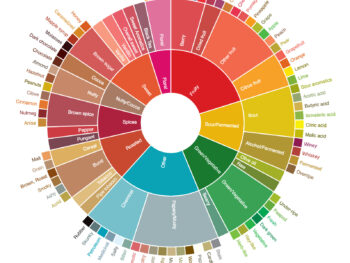ホテルのチェックインを済ませ、ひと息つくと、
夕方の5時過ぎになっていた。
東京に出てくるのは、暫くぶりである。
今回は、
大切な、とても大切な友を見送るための上京になった。

私は、上京すると、
いつも飯田橋にあるこのホテルを利用する。
大した理由はないが、あえて云うなら、長年住み慣れた西神田にほど近い場所にあるからだ。
思い出が残る東京の街はいくつかあるが、神保町界隈は、私にとって特別な街なのである。
学生時代に通い詰めた街であり、社会人としてスタートを切ったのも神保町。
そして、結婚後の子育ては、西神田で過ごした。
世間一般の基準からすると、決して住みやすい街とは言えないが、そこは「住めば都」である。
多少の不自由さを感じながらも、すっかり我が街と呼べるほど、愛着のある街になっていた。
3年前に父親が病に倒れ、
急遽、実家の製材所を引き継ぐことになり、妻と二人で郷里へ引っ越したのだが、
上京すれば必ずこの街に戻ってくるようになった。
友の訃報を受けたのは、二日前のことである。
夜の11時過ぎ、一本の電話がそれを知らせた。
携帯を手に取ると、古い友からの電話であることを告げていた。
学生時代から付き合いのある長瀬祐一からであった。
「やあ、長瀬。久しぶりだな。いつ振りだろう?
もう、一年以上はご無沙汰になるか……。
元気でいるかい?」
「……」
こちらの呼びかけにも、彼はしばらくの間、黙り込んでいた。
普段の彼なら、愛想のよい言葉を返してくるはずだが、
その日の彼は、少し様子が違っていた。
「長瀬、……、どうかしたのか?
こんな時間にかけてくるなんて……、何かあったのか?」
「……」
私の呼びかけに少し間を空けてから、彼は、ようやく重い口を開いた。
「夜分にすまないね……。
……、お前さん、元気そうじゃないか」
聞きなれた友の声が耳元で響くが、どことなく重い空気をまとっていた。
「ああ、こっちは、どうにかこうにか元気でやっているよ。
そっちはどうなんだい? 役員の椅子は、座り心地いいかい?」
長瀬は、昨年の春から子会社の役員に収まっている。
彼と私は、大学卒業後、同じ会社に就職した。
私生活では良き友であり、仕事上の良きライバルでもあった。
私が早期退職し、郷里へ引っ込んでからしばらくして、
長瀬から子会社へ移るという報告を受けた。
「ついに俺も用済みになっちまった……。
詰み……ってところかな? これからは、消化試合の会社勤めになりそうだよ」
などと、彼には珍しく弱音を吐いていたことを思い出す。
本社での現役続行を望んでいた彼には、納得のいかない人事だったのだ。
「役員なんて名前ばかりさ……。
仕事らしい仕事は、無いに等しいんだ。
定時に出社して、毎日、定時に退社しているよ。
それの繰り返しの日々……。
時間を持て余して、逆に気が滅入っちまう」
「ほお。
それは、良いご身分だ!
……、でも、仕事一筋のお前には、やはり辛いか……」
「……」
いつもの彼なら、本社の役員連中に対して、憎まれ口の一つでも吐きそうなものだが、
この時は、その気配を微塵も見せなかった。
「定時に退社しているってことは、三鷹の自宅からかけているのかい?」
彼の住まいは三鷹にある。
親から受け継いだ一軒家で、奥さんと二人暮らしをしている。
誰もが認める仲の良い夫婦だが、子宝には恵まれなかった。
彼が口にすることは無かったが、
我が家の子どもたちが懐いていた様子からしても、
彼が子ども好きであることは明らかであった。
「いや、家からじゃない。
……、神楽坂の店から、かけている……」

神楽坂の店。
それは、タイムファイブのことを指している。
私たちの間で、神楽坂の店とは、この店のことでしかない。
私たちが学生時代から親しんだ隠れ家的なジャズバーだ。
そして、長瀬がこの店を仕事で利用することは決して無い。
長瀬と私、それにもう一人、
二人の共通の大切な友にとっても特別な店であった。