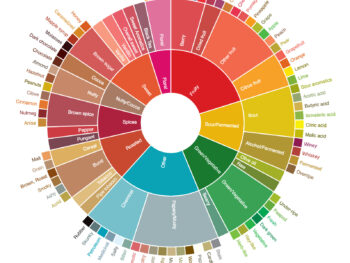明日の告別式を前に、どうしても長瀬と私の二人で悦子を偲びたかった。
また、それは三人の純粋な想い出が語れるこの店でなければならないと思った。
長瀬の話では、悦子の危篤の知らせを彼女の母親から受け、急ぎ駆けつけはしたものの、
言葉を交わすこともなく彼女は息を引き取ったらしい。
救いは、最期を迎えたのが入院先の病院ではなく、住み慣れた雑司ヶ谷の自宅だったということだ。
本人と母親が、強く望んでのことだったそうだ。

母親と娘の二人暮らしが長く続いたこともあってか、
雨宮家の母娘関係の絆は、世間のそれより一層強いものであったことを長瀬が語ってくれた。
苦しかったであろうにもかかわらず、彼女の最期は、
瘦せ細ってはいたものの、とても穏やかな表情で天に召されたとのことである。
長瀬と悦子は、小学生から大学生になるまでずっと一緒に進学し、
お互いの家も家族ぐるみで付き合いのある間柄だった。
大学卒業後も、家同士の往来は続き、恐らく悦子の意向もあってのことだろう、
親族以外で彼女の最期を見届けたのは、長瀬ただ一人である。
私も彼女の母親とは何度も顔を合わせ、一時期、親しく接していたこともあったが、
二人の間の事情を知る母親としては、直接私に連絡を取るのは避けたかったようだ。
ただ長瀬によると、
必ず私にも彼女を見送ってほしいと念を押されたそうである。
学生時代の長瀬にとっての私は、親友であると同時に恋敵でもあった。
今でも彼は、悦子のことを「永遠の片想いの女」と呼んで憚らない。
同時に、私のことは「永遠の恋敵」と呼ぶ。
幼馴染で、いつも一緒にいるのが当たり前だった彼女が、
気が付けば、地方から出てきたばかりの野暮な男に奪われてしまったのだそうだ。
確かに、この「野暮な男」という言葉には聞き覚えがあった。
ただし、それは学生時代の悦子から聞かされた言葉だった。
「あなたって、一見パッとしない野暮な男のようだけれど、本当は違うのよね。
私は、そこがとっても気に入っているの。
あなた、気付いていたかしら?
だから、どうかそのまま、いつまでも変わらずにいてね。
私の『野暮』な恋人くん!」
そう言って笑いながら私の胸を両手で押し、
背を向けたかと思えば満面の笑顔で振り返って見せる……。
その彼女の言葉と仕草が、鮮やかに甦ってくる。

お互いに恋人として意識し始めたのは、満開の桜の木の下を二人で歩いた
あの日からのことであった。
それから暫くして、二人は結ばれた。
当時のことを長瀬は、いまだに毒々しく振り返る。
私としては、長瀬の手前、二人の関係を隠せるものなら隠し通したかったのだが、
当の悦子はと言うと、まったく気にも留めない様子だった。
「どうして隠す必要があるのかしら?
それって、逆に長瀬に対して失礼だと思わない?」
悦子と話し合った翌日には、
彼女は、あっさりと二人の関係を長瀬に伝えていた。
当然、私は長瀬に対して気まずい日々がしばらく続いたのだが、
結局は彼の方から折れることになった。
「悦ちゃんを悲しませたら、絶対に許さないからな」
恐らくそれは、若い三人の中での儀式のようなものであったと思う。
その長瀬の言葉を私が受け入れ、悦子の前で握手を交わし、
これからも変わらぬ友情を育むことを二人して彼女に約束した。
いや、正確には、彼女に誓わされたと言うべきか……。
「それで、よし!」
悦子は、満足そうに笑っていた。
その後も、彼女の態度が変わることは決してなかった。
彼女は、いつものように、彼女のままであり続けた。

当時のことを長瀬は、
「本当は、ぶん殴ってやりたかったさ」
と真顔で話す。
「でもさ、悦ちゃんに言われたんだよ……。
お前さんのことを大切に思うように、俺のことも大切だって。
人として大切に思う部分は、まったく同じだって。
大切な人だから、俺のことも大好きだって。
そう……、確かに悦ちゃんは、そう言ってくれたんだ。
ただ、好きという感情とはまた違った、俺には感じることのない別の感情を
お前さんには感じているんだって……。
悦ちゃんにさ、そう言われちまったら……」
そう言いよどんだところで、彼は私の顔を正視し、
「だから、お前さんは、いつまで経っても俺の恋敵なんだよ」
そう言って苦笑しながらグラスを傾けた。
現在の奥さんを愛するようになるまで、
彼が悦子に恋していたことは私が一番よく知っている。
それも、一時的な恋愛感情などではなく、長い歳月育んできたものであった。
恐らく、私がそうであるように、妻への愛情とは別に、
プラトニックな彼女への恋心を今でも持ち続けているのだろう。
その心情の根底にあるのは、長瀬も私も、彼女への「敬愛の念」に違いなかった。
二人にとって、悦子という女性は、いつまでも特別な存在であり続けたのだ。
悦子と恋人関係になってから間もない頃、
彼女がどうして私を選んだのか知りたくなり、それとなく尋ねたことがあった。
それに対して彼女は、
「いつも伝えているじゃない!」
とはぐらかし、例の「野暮な男」のフレーズで切り返した。
そんなある日、タイムファイブでのことである。
彼女がマスターにリクエスト曲を手渡した。
そこへ流れてきたのが、
チェット・ベイカーが歌う「マイ・ファニー・バレンタイン」だ。
トランぺッターのチェット・ベイカーが、気だるく歌い上げる一曲だ。
今でこそ、彼の「マイ・ファニー・バレンタイン」は、
ジャズのスタンダードとして認識されているが、当時はまだまだ異色と評されていた。
この曲の代表的な歌声は、あくまでもフランク・シナトラやエラ・フィッツジェラルド、
それにサラ・ボーンたちであった。
それだけに、彼のアンニュイな歌声は異彩を放っていた。

曲が流れている間、悦子はキャンパスノートに英文を綴った。
何を記しているのか私が尋ねると、
「この曲の歌詞よ」
と言って、曲が終わると私に手渡した。
そのことが何を意味しているのか理解しかねていると、
「あなた、知りたいのよね?」
彼女は、両肘をテーブルにつき、私の顔をまじまじと覗き込んだ。
そして、
「あなたに恋した理由よ。
私のあなたへの気持と、ほとんど同じ内容がここには書かれているの……」
まるで、ひそひそ話をするかのような素振りで、彼女流に訳した歌詞を聞かせてくれたのだった。
それ日以来、この曲は、私にとって大切な一曲になった。
その話を聞いた長瀬が、
「それは初耳だな。
そうか、お前さんは、悦ちゃんにとってのバレンタインだったのか」
そう言いながらグラスを掲げた。
「それなら、リクエストしなきゃな。
きっと、悦ちゃんも喜んでくれるだろう」
彼は、マスターを呼び止め、この曲のリクエストを依頼した。
しばらくすると、彼女と一緒に聴いた
若かりし日のチェット・ベイカーの歌声が店に流れ始めた。
彼女が訳した歌詞は、今でも覚えている。
そして、いつも彼女が言っていた
「いつまでも変わらないあなたでいてね」
という言葉が、歌詞と重なり、思わず涙が頬を伝った。
あれは、悦子の心からの願いだったのだ。
彼女は、いつも願いを込め、その言葉を口にしていたのだと、
今なら充分すぎるほど理解することができた。
しかし、若かった頃の私は、
彼女のその願いを受け止めることができなかったのである。
大学を卒業し、就職後も悦子との関係は続いていたが、
私は、いつしか仕事にのめり込み、同時に、大都会の人間に成り切ろうともしていた。
いつの頃からか、
悦子とはすれ違いが生まれるようになり、二人で話し合った結果、距離を置くことにした。
「あなたが、あなたらしく生きることを祈っているわ」
その言葉を最後に、二人の恋愛関係は、終止符を打った。
それから数年後、私は現在の妻と結婚した。
当時の悦子は、音楽雑誌の編集者として活躍していた。
長瀬から、彼女の近況は常に知らされていたし、雑誌を通じて、
活躍ぶりを確認することもできた。
私の結婚式にも、彼女は長瀬と一緒に列席した。
私はどうかとも思ったのだが、長瀬から彼女の参列を強く求められ、
結局、押し切られてしまったのだ。
式を迎える数日前に、三人で会うことになった。
長瀬がセッティングしてのことである。
三人の関係が、これからも壊れることのないようにと、彼なりに気を効かせてのことだったのだろう。
三人揃えば、否応なく学生時代の思い出が甦る。
ところが、気まずい雰囲気だったのは、どうやら私だけのようで、
悦子は、相変わらず彼女のままであり続け、私の前では凛とした姿を見せていた。
「私にとってあなたは、いまも変わらず大切な人よ。
それは、長瀬も同じ。
どうか、そのことだけは忘れずにいてほしい」
その彼女の言葉に、私は救われた。
そしてその日、私は、いつまでも良き友であり続けることを彼女に誓った。
それから以降の三人の関係が、
穏やかに過ごせたのも、ほかならぬ悦子と長瀬のおかげであった。
「今だから明かすが……」
と前置きをし、長瀬が、私の知らない当時の悦子の様子を語ってくれた。
それによると、私が他の女性と結婚することを知った彼女は、ひどく動揺していたこと。
結婚式への参列も、最初はためらっていたのだが、長瀬の説得により、ようやく出席を決めたこと。
また、三人が再会したあの日、私と別れた後で、
長瀬と二人この店でグラスを傾けながら、今にも消え入りそうに、一人涙を流していたこと。
どれも私が知らない彼女の姿ばかりであった。
そして、
「私は、私であり続けるの。
だって、何も変わっていないもの。
いつまでも変わることはないと思う……」
と彼に伝えたのだという。
その後、彼女は一人で歩むことを選んだ。
恐らく、その選択について語った最後の想いが、長瀬が聞いた末期の言葉、
「私、後悔なんて、していないのよ。
自分が選んだ人生だもの。
これで、良かったんだって……、心から、そう思っているの」
だったのだろうと、彼が明かしてくれた。
マイ・ファニー・バレンタイン。
あの日、君は僕をそう呼んでくれた。
マイ・ファニー・バレンタイン。
今夜、僕がそう呼ぶことを果たして君は、許してくれるだろうか。