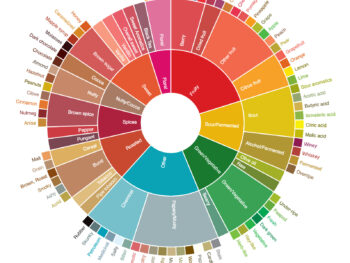ホテルの部屋の窓は、東の方角を向いていた。
部屋からは、水道橋、御茶ノ水方面が一望できた。
御茶ノ水にある高層ビルのガラス面に、西日が照らされていた。
それは、もう間もなく日の入りの時刻であることを告げていた。

長瀬との約束の時間は、午後6時。
彼の退社時間に合わせて、そう決めていたのだ。
ホテルからタイムファイブまでは、歩いて15分もあれば到着する。
今から外出の準備をすれば、ちょうどよい頃合いである。
身支度を整え、5時40分にホテルを出ることにした。
東京の桜の開花は、もう間もなくであった。
JR飯田橋駅の西口から市ヶ谷方面は、すっかりピンク色に包まれていた。
まだ蕾のままだが、色づき加減から開花が近いことを知らせていた。

学生時代、そう、あれは確か悦子と知り合って2年目の春のことである。
彼女に誘われ、その日は二人だけで満開の桜の木の下をただただひたすらに歩いた思い出がある。
英国大使館前でおち合い、
そこから千鳥ヶ淵、靖国神社、そして早稲田通りを下り飯田橋へ。
飯田橋から市ヶ谷へは、東京逓信病院側の南面を歩き、
市ヶ谷から飯田橋への折り返しは、北側の外堀通りを下った。
歩きながらどのような会話をしたのか、
今となってはもう思い出せないが、彼女と過ごす眩しい時間が、
いつまでも続いてほしいと願っていたことだけは覚えている。

悦子の高校時代からの女ともだちは、
マイカーを持つボーイフレンドとのドライブを楽しんでいたが、
彼女は、そうしたことにはまったく関心を示さなかった。
二十歳を迎えたばかりの彼女は、
人に左右されることなく、自分の頭で考え、判断し、そして行動に移すことのできる、
他に依存しない、一身に独立した女性だった。
神楽坂下の交差点を渡り、ふと後ろを振り返って見た。
今でも、そこにはカナルカフェがある。
初めて二人だけで過ごしたあの日、彼女に連れられこのカフェでランチをとった。
悦子は別として、田舎から上京してきたばかりの青年には、
少々不釣り合いに見えるお洒落な店だったが、
今でも海外の水上レストランを思わせる雰囲気は当時のままである。

思い返せば、彼女との思い出が残る店は数え切れない。
これから向かうタイムファイブも、そうした店の一つである。
悦子は、彼女が高校生の時に父親を亡くしているのだが、
その亡くなった父親の影響を受け、もっぱらジャズを聴いていた。
大好きだった父親が遺した膨大な量のLPアルバムを彼女は1枚も欠かすことなく
聴き込んでいたのだ。
同じように、父親が贔屓にしていたこの店も、彼女は愛して止まなかった。
お酒が飲めるようになってからというもの、
悦子がタイムファイブに行く際は、必ず私と長瀬を伴うようになっていた。
長瀬は中学生の頃、彼女の父親から直接ジャズの薫陶を受けた強者だった。
私と知り合った頃には、既に筋金入りのジャズ通であった。
同年代の子どもたちが、歌謡曲やポップミュージックに夢中だった頃、
この二人は、アート・ブレイキーやジョン・コルトレーン、
ビル・エヴァンスにセロニアス・モンクについて語り合っていたのだ。
その二人のジャズ談義に割って入るのは、最初の頃は困難を極めたが、
そのうちに私もどっぷりとジャズにハマり、三人で夜遅くまで店で語り合ったものだった。
他の常連客がリクエストする合間を縫っては、話題に上がった曲をマスターにリクエストする。
そんなことを繰り返していた。
マスターも心得たもので、
幼い頃から知る悦子の男ともだちを大切な客としてもてなしてくれた。
残念ながら、その当時のマスターは数年前に他界し、
現在は、店の常連客だった有志が、店を譲り受け営業を続けている。
私が店に到着したのは、約束の5分前だったが、長瀬は既にカウンター席に腰を下ろしていた。
店のカウベルが鳴ると、彼は肩越しに振り返り、右手を大きく上げ自分の存在を知らせた。
見渡したところ、他に客はまだいない。
店内には、ビル・エヴァンスの「マイ・フーリッシュ・ハート」が流れていた。
店の雰囲気は、昔のまま変わることはない。
長瀬と顔を合わせるのは1年ぶりである。
椅子から立ち上がった彼は、大きく両手を広げ私を迎え入れた。
そして、握手を交わし、再会の喜びを分かち合った。
私はスコッチをロックで注文し、
しばらくの間、お互いの近況などを話しながらグラスを傾けた。
最初の一杯を空けるまで、長瀬も私も悦子の話題には触れなかった。
いや、触れられずにいたと言った方が正しいだろう。
二人にとって、彼女の死を受け止めるには、それなりの覚悟を必要とした。
悦子の名を口にしてしまえば、
途方もない喪失感に打ちひしがれてしまいそうで怖かったのだ。
6時半を過ぎた頃から、他の客もポツリポツリと訪れ始めていた。
二人の事情を知るマスターが、
気を効かせて私たちを奥のテーブル席へと案内してくれた。
それがキッカケとなり、
私は、ようやく悦子について、また、彼女と過ごした日々について追憶する覚悟を決めた。